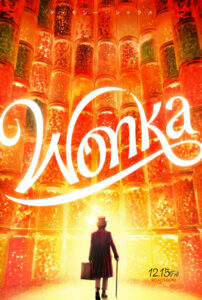人生とは、ほんとうにたくさんの網の目のような、螺旋を描きながら向こうへと続く出会いと別れに満ちていて
それはいつ懐かしんで思い出しても、ずっと胸の奥を優しく温めてくれる。
一刻も忘れてしまいたい辛い記憶も、最後まで優しかった記憶も、いつでも取り出して抱きしめることができて、それは誰にとってもきっといくつかそういう大切だった出会いがあるはずで
人生の中で道に迷ったときに、それは、真っ暗な道を照らしてくれる灯りになる。
わたしがよく、何度も辛い局面でいつも想ったのは、バーモントの家族だった。
アメリカのバーモント州というところに小さなオーガニックファームとInn(貸別荘みたいな宿)のコミュニティがあって、仕切っていたユダヤ人の家族に、なにかあるごとにとりたてて用事もなく連絡した。
ほぼ日本人のいないエリアで、ことばも宗教も文化も肌の色も何もかも共通するものは無かったけれど、そこはわたしの故郷だった。昔から、よく知っているような人たちの集まりで、ぽつんと彼らの中に放り込まれた瞬間から、わたしは彼らに歓迎されて、その一部になった。
建物がどんどん移築して大きくなる前の、まだこじんまりしていた頃から私はそこを出入りしていて、テレイオンホロンというギリシャ語の名前のかわいい看板がかかった、白い木造の端正な宿があって、大きな部屋では時々ヨガとか瞑想のリトリートがあったり、誰もいないときには、こどもたちと一緒に、そこにとれたての野菜をひっくり返して寝転んだ。
その白い木造の建物の一室にわたしは住み込んでいて、毎日こどもの世話をしたり、ハーブの茎から葉っぱをはがしたり、ときどき近所の本屋に壊れた車で無免許で走ったり、金曜日の夜のShabbosのディナーで彼らと一緒に祈った。
どこもかしこも心地よい風が吹いていて、今も苦手なベッドにシーツをかけるのだけは、下手だったけど、そこはいつも何が起こっていても愛に満ちていて、わたしが最も安心する場所だった。
当時つきあっていたMaxが、研究だか仕事だかのためにイスラエルやウガンダやいろんな場所に行っては実家に戻る間も、わたしはそこで家族と一緒に過ごした。
あんな生活ができたらと、いまだにずっと思う。
Teleion Holonは、わたしのアメリカ生活の始まりの基盤になった場所で、ニューヨークに行く前の文字通りHomeでその台所で過ごした時間が、この先いつか、自分が持ちたいSacred Placeだ。
そこは、不思議と寂しくはなかった。
この人生の始まりから終わりまで、孤独じゃなかった時間はあっただろうかと思い出せないほどに、深い孤独の中で生き続けたわたしの、稀に見る孤独じゃない暖かで包まれるような時間。
日本にいるときは、ほとんど生まれた頃から浮いていて、変わり者だと言われなかったことはなくて、それはうまく活かせれば歓迎されることもあるけど、今でもわたしを苦しめる。
アメリカにいた時の自分は、ただ自然に世界に馴染んでいた。
いろんな人種も宗教も考え方も性格も、すべてが混じり合って成り立っているその場所で、わたしはきちんとみんなの中で、受け入れられたり、助け合えたり、愛されたり大切にされたことは、
本当に幸せなことだったな、とそう思う。
その台所で、ときどきMaxのラップトップ(ノートパソコンのこと)を開いて、音楽のPlaylist を鳴らした。
全然好きじゃないジャンルのものや、謎のワールドミュージックが溢れている中で、わたしが唯一気に入って「あれ、かけて」と言ったのが、ユダヤとウガンダの掛け合わせの曲だった。
自分の好きなジャズやこざっぱりしたクラシックや、アンビエントの曲とは対称的で、そこからどこかの国のルーツや誇りや、文化や土の匂いが立ち込めるような閉鎖的にも聴こえる音楽。
おなじような理由で、わたしは日本の伝統音楽も苦手で、ユダヤの独特の、ほんと黒歴史かよみたいな新規臭い音楽😂のメロディも、好きなのもあったけどほとんど興味がなかった。さらに言えば、ウガンダとかアフリカにも、縁もゆかりもなくて、とても遠い世界だなと感じるんだけど
でも、このAbayudayaだけは、なぜか何度聞いても不思議な温かい感覚になった。
この地球の上で、いろいろなものを大切に守りながら、育みながら、とても遠い国で
地に足をつけて、生きているひとたちがいる。
迫害されても、ひどいレッテルを貼られながらでも、それでも自分たちのアイデンティティを脈々とつないでゆくために、世界のどこの国で何人として生きても、独特の立ち位置で彼らが守ってきた「ユダヤ」というあり方。
日本は、豊かすぎて、なにかが溢れすぎていて、たくさんのことが麻痺しているような気がする。
人が人して生きるために、忘れてはいけない心のことや、地域や、となりにいるひとたちとのつながりを大切にしてゆくことや、自分には、その場所でひとと関わってゆくだけの価値があると感じること。
いのちの重みや、「生きる」という素朴な感覚から、離れすぎてしまったんだろうと思って、今日はひたすらに泣いた1日だった。
遠いどこか足を運ぶこともない国で、貧しく飢えたこどもたちの気持ちや
明日生きられるかわからない環境でいのちをぶらさげている人々の気持ちは、
この国にいれば、別世界みたいに感じるかもしれない。
それは同じ世界にいきる人間として、悲しいことだなとおもった。
Abayudayaの名前のなかに、ユダヤという名前が入っていて、英語でユダヤはJewなので、
ユダヤって何語なんだろうと思うけど、
それもまた、このアルバムを特別に感じた最初の理由だったかもしれない。
わたしたちは日本人だし、日本から出たことない人もいっぱいいるし、
世界を知らないことは当たり前のことかもしれない。
でも、ウガンダの、ユダヤ人が奏でたメロディが、こんなふうに日本の夏に届くこともあって、
わたしたちは同じ続いた空の下で、生きている。
土の匂いと、嗅いだことのないスパイスの匂いと、雄大な自然のなかで荒々しい土地を美しく覆うような信じられないほど美しい夕日が沈んでいく荘厳さのことを
行ったこともないけど、感じるよ。
温かく重なる歌声が、異質なものへの抵抗や、助け合うことができないこの国で、ずたずたになったわたしの心を包んでく。
わたしたちは、決してひとりじゃない。
たとえその場所ではたった孤独に闘っていたとしても、この地球や空や美しい景色は、必ず調和と愛のことを教えてくえる。
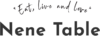
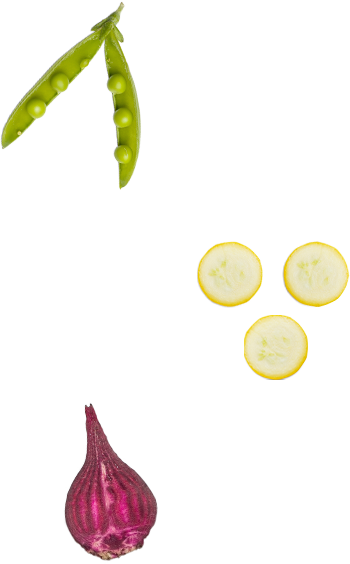

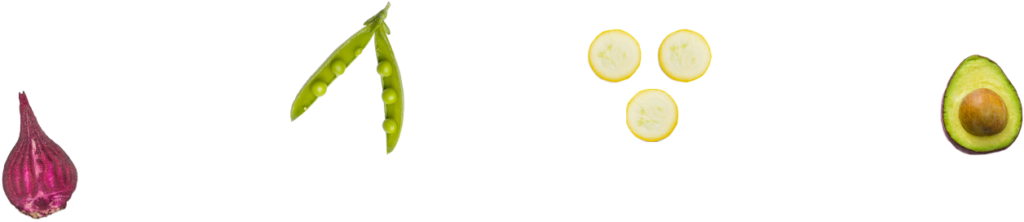

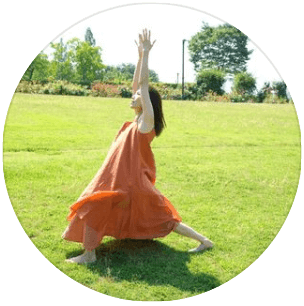 世界中に愛と癒しが行き渡り、みんなが支え合って生きてゆけますように💕
世界中に愛と癒しが行き渡り、みんなが支え合って生きてゆけますように💕