大根おばさんが来て、明日の母の日のケーキを焼いて、夜渡した翌朝。
おかあさんは、死んだ。
とても穏やかに、お父さんとたおくんが見守る中で、おかあさんは静かに息を引き取った。
ああ疲れたから、本当疲れたから、やっと眠ろうって感じに。
早朝にわたしが駆けつけたとき、息をひきとったばかりでまだ身体は温かかった。
「おかあさん、母の日だから、来たよ…」
「まい、来たよ….」
そう言って、そばに行って
まだ温かい、手を握った。
1ヶ月くらい前に、ちょこちょこ顔をだす中で
何が食べたいか訊いて、その日によって具合が悪そうだったり、すこし食べられたりする中
お母さんは、「ケーキが食べたい」と言った。
これまで家族の誕生日に、ときどきケーキを焼いて持っていった中で、それが本当に喜ばれているのか、食べられているのか、実際は糖尿だったお母さんはケーキなんかもらっても食べないのか、
よくわからなかった。
ただわたしは、誕生日は、誰のどんな誕生日であっても、その日は尊い日だとおもっていて、できるかぎり焼いた。
私の実家は、誰も誕生日を祝わない家で、みんな誕生日を忘れたり、プレゼントをかったり、ケーキを食べたりしない家だった。
唯一わたしだけが、それを祝おうとたったひとりでケーキを焼いたり買ったりして、どうして誰も、大切な日を大切に扱わないのかが、よく理解できなかった。
まもなく死を迎えようとしていたお母さんは、食べたいものを食べた。糖尿とか病気とか関係なく、食べられそうなものをがんばって食べていたとおもう。
ケーキが食べたいといったお母さんは、いままで見た中で、いちばんなんていうか、わたしに素直というか、やわらかかった。
「ケーキが食べたいの?いちごのやつ?どのケーキ?」
すごくぼんやりと「うーん、ケーキ」と言われて、
おかあさんがケーキが食べたいことはわかったけど、何を指すのかよくわからなかった私は、訊いた。
すると、ぼんやりしたまま、すこし弱くて、あたたかい声で、
「おかあさん、まいの作ったケーキが好きなんだよねぇ。なんか、ほかのもいいけど、まいがつくるあのスポンジが、おいしくて。あれが好きなんだ」
とそう言った。
わたしの焼くケーキは、いつもお店で売ってるみたいなふわふわにはできなくて、なぜかぼてっとして、目が詰まって素朴になる。
でも食べると、まあまあ美味しくて、すごく美味しくは無いんだけど、また食べたくなるような、
そういう手作りっぽいスポンジだった。
わたしは、おかあさんが、わたしの作ったケーキを好きだったことを、その日初めて知って
「そうか。わかったよ。じゃあまた作って持ってくるからね。」
と言って
スーパーで、生クリームといちごを買った。
きれいだとも、かわいいとも、賢いとも、よく描けたねとも、うまくできたねとも、おいしいね、とも
母から一度も褒められたことがないわたしが、さいごに
はじめて褒めてもらった瞬間だった。
4月の終わりのお父さんの誕生日に
おとうさんはチョコケーキが好きなので、いつもはイチゴのショートケーキは作らないんだけど
その日は、おかあさんが食べたいといったケーキを作った。
その後行ったときも、「ケーキは?」と言っていたおかあさん。
「まいが、ケーキを焼いて持ってくると言っていたから」と
お父さんに話してたと、お父さんはそう言った。
あと何回、おかあさんにケーキを焼けるんだろう。
そうおもいながら、4月に焼き、母の日に焼いたスポンジを
おかあさんは最後、食べることはなかった。
母の日に死ぬなんて、おかあさんらしいというか
潤の誕生日に死ぬなんて、おかあさんらしいというか
数日間の間
ほんとうに、いろんな想いが交錯して
悲しみとかよりも、
とてもふしぎな感覚だった。
早朝に息をひきとったおかあさんの代わりに
ありつける予定ではなかったケーキに、よばれることになって
すぐに来てくれたおばさんたちと一緒に
母の日の
おかあさんのケーキを
朝ごはんに食べた。
こどものころ、たまに
買ってきたケーキを朝ごはんに食べる日は、ぜいたくで嬉しかったことを思い出した。
この先おなじレシピで、いちばん普通の、よいケーキを焼くたびに
わたしはきっと
おかあさんを想うだろう。
「おかあさん、まいがつくったあのスポンジが、すきなんだよねえ」
その最後に言ってもらった声をわたしはきっと
一生たいせつに、
この先も生きるのだと思う。


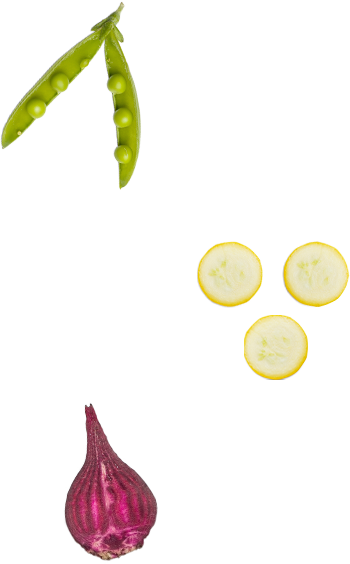



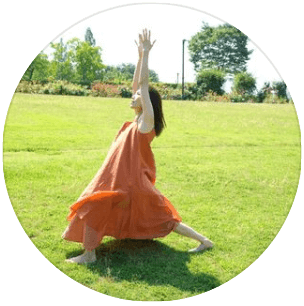 世界中に愛と癒しが行き渡り、みんなが支え合って生きてゆけますように💕
世界中に愛と癒しが行き渡り、みんなが支え合って生きてゆけますように💕



