2019-10-15 再投稿
その白人の男はセックスまでも神経質な男だった。
なんていうか、くせのない普通のセックスは、比較的嫌いと言うわけではない。ただ淡白でも暖かみとか、不器用でも優しさとか、そういう人間ぽい営みがわたしは好きだからべつに普通でよいのだけど、彼の場合は普通というかは、神経質な感じがした。
とりたてて不具合があったとか、何か言われた記憶は全くなくて、酷くノーマルな短いセックスは、気持ちよくも痛くも痒くもなくて、当時特定の恋人が欲しかった私は、彼にその気がないことを知って、そのうち会うのをやめた。
何より綺麗な身体をしている人だったので、適度に鍛えられてメンテナンスされてる白人の身体というのは、いいんだけど、自分にとっては味気ない。
ちょっと腹がたるんでるとか、微妙に勃ちにくいとか、そんなのがひとつやふたつあったほうがキュンとする。
マンハッタンの下の方にstudioと呼ばれる一人暮らし用の部屋を借りていた彼の部屋に行くと、とてもおしゃれとは言えないチャイナタウンの一角にそのピアノが置かれた狭い部屋があって、ときどき上半身裸のままでラフマニノフのピアノが鳴るのがわたしは大好きだった。
セックスはつまらなかったが、そんなに情緒的でもない彼の淡白なピアノは、わたしの好きな曲をリクエストできたし、指先が何かを奏でてゆく姿というのは、どれだけ見ていても飽きない。
ときどきそれを眺めて、気が済んだらわたしは仕事に戻り、自分の部屋で眠った。
ところでセックスはさておき、食べるものに神経質な人間は、わたしにとっては吉と出るか凶とでるかのどちらかである。
そして、その男は、大吉だった。
乾いたセックスを終えて、眠り朝起きると、彼が簡単な朝ごはんを用意してくれた。
ベーグルとかソーセージのいわゆるアメリカンブレックファーストじゃなくて、それはオーガニックのきゅうりの入ったすがすがしい初夏の味がするスムージーだったり、いつもわたしが食べていたような山盛りの果物に、趣味のいいグラノーラがかかっているものだったり、色々だったけど、とてもセンスが良くて、初めてアーティチョークを食べて、名前しか聞いたことのない野菜を実際口にしたのも、それがタケノコに似た食べ物であることを知ったのも、彼のアパートだった。
ある朝そして、彼はワッフルを焼いた。
”クランベリーは食べたことある?”
彼はわたしにそう訊いて、当時クランベリーが食べたことがあったのかどうかもよくわからなくて、ぼんやりと記憶を手繰り寄せていたわたしに彼は
「ワッフルにクランベリーを入れるのが好きなんだ。」とそう言った。
それで、ジュワジュワと生地が泡立ってくるまだ蓋を閉じる前のワッフルメーカーに、冷蔵こから出したての真っ赤な生のクランベリーを散らして、それで一気に熱い蓋を閉じるのだった。
ワッフルメーカーは大抵電気のであればフッ素加工がしてあるものなので、汚れなんかはほとんど気にしなくてもいいのだけど、クランベリーに関してはすごくドキドキした。
まるでエスプレッソメーカーにコーヒー豆じゃなくてみかんを突っ込んで実験するみたいに、その紅い実が弾けて汁が飛び出したりしてどうなるのか、焼けるまでの短い時間をハラハラしながら見守った。
その頃わたしはまだ結婚する前ふらふら遊んでいた頃で、温かな家庭にワッフルメーカーを所有していなくて、その構造みたいものをよく知らずにいた。
焼きあがったワッフルは、甘い匂いの側からルビー色の宝石がキラキラ煌めくようだった。
それまで結構長い間ベジタリアンの食環境でどっぷり現場に関わっていて、果物や野菜にはほとんど精通していて、スコーンやらビスケットやらを焼くことも日常的に触れていたはずなのに、なんだか生まれて始めて見た、明治時代に外国人が持ち込んだ舶来のお菓子に衝撃を受けるように、クランベリー入りのワッフルを目にしたような気がした。
クランベリーというのは、砂糖漬けされたドライフルーツは一般的で、よく日本でも見る。
しわくちゃの縮んだ濃いピンクのレーズンみたいなやつだけれど、日本で生のクランベリーを目にしたことはこの人生で一度もない。
先日一度、ドイツに住むイラストレータさんから「この間はじめて生のクランベリーをいただいて、まいさんを思い出しました!」とメッセージをいただいて嬉しかったのだけど、ドイツですらほとんど日常に登場することのない幻の実なのだった。
そしてアメリカでも、生のものは季節ものでとても短い期間しかスーパーに並ばない。
並ばない上に、調理しなければ食べられないので、多分おかし作りや何かしら料理好きな特定の人にしか手が届かないようになっている。
私はそのロウワーイーストの男のStudioで、初めて、ワッフルに入る前の、生のクランベリーをおそるおそる一粒細い指でつまみ、齧った。
食べた瞬間に首筋に鋭い稲妻が走るくらいにそれは、酸っぱいなんてだけじゃ言い表わせないくらい酸っぱくて、硬く強すぎて、とても食べられる代物じゃなかったことに驚いた。
こ、これが、ク、クランベリーだったとは!
そして、もっと驚いたのが、ワッフルに入ったほうの、クランベリーだった。そこに火を通すと、魔法みたいに味も質感も和らいで、ちょうど甘い焼き菓子にそれが溶けて、グシャっと形を無くした時に紅い汁が適度に生地に混ざりこんだとき。
そのタンジーな酸味は、甘いワッフルの香ばしさに見事に溶け込んで、他では代用できないような信じられないアクセントになるのだ。
甘いものに、酸味が全体に混じってるのではなくて、それがランダムに散らばる味は、他にも考えるとあるにはあるけど、例えばチョコレートケーキのラズベリーソースとか、オレンジのマーマレードとマフィンとか。
ただ、これまで食べたこのある全てのマリアージュと比べて
クランベリーは、ただ一線を画していた。
それは写真でいうところのコントラストみたいなもので、どこかがグッと強く前に出るときに、どこかはグッと後ろに下がる、あの潔さと濃い臨場感のある味。いままでにあじわったことのない稲妻が走るような美味しさだった。
柔らかな甘みのワッフルと、ツンと刺すようなクランベリーの酸味、焼きたてでまだ角が立つクランチーな食感どれをとっても文句がないのに、ザブッと上からオーガニックのメープルシロップをかけてそれを食べたときの、いまだかつてない贅沢は、一瞬でわたしを虜にした。
わたしは、これまでのジャムやドライフルーツに抱いていたクランベリーへの普通の好意から、その後その紅い実に尊敬と心からの敬意の眼差しを込めて賞賛を抱くようになって、今に至る。
それは、魔法の実。
英語にはoutstanding という単語があって、抜きん出てるみたいな意味だけど
それはストロベリーでもブルーベリーでもラズベリーでもブラックベリーでもない、
そんなメジャー感を一掃してでもすぐにそれとわかる、ベリーだけど、ベリーじゃない、クランベリー。
その日から何年か経って結婚したわたしは、クリスマスプレゼントにカルファロンのワッフルメーカーをサンタという名の家族に貰い、そのあと離婚して帰国するまでクランベリーのワッフルを焼き続けた。
バターと油と砂糖の量を、客によって微妙にレシピを使い分け、そのひとの舌に届くときに極上のワッフルへと様変わりするように。
そのルビー色の実を、帰国してから一度もみたことがなかった数年後の秋の日、小さなベランダにクランベリーの苗を植えた。
夢みたいに可愛い宝石が、毎朝カーテンを開けると目に飛び込んでくるみたいだった。
クランベリーのワッフルのレシピは、無くしてしまって
どこにもないんだけど、またいつか発掘したらぜひレシピに加えたい。


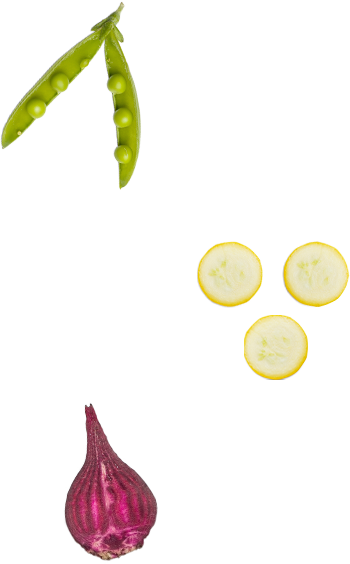



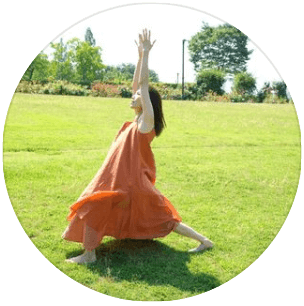 世界中に愛と癒しが行き渡り、みんなが支え合って生きてゆけますように💕
世界中に愛と癒しが行き渡り、みんなが支え合って生きてゆけますように💕



