誰かを愛するのではなく、愛する人を愛するという、本当のチャレンジに。

その腕の中で眠った、初めての夜だった。
それは、柔らかくて、優しくて、思っていたよりもうんと大きくて、温かかった。
わたしは静かに泣いて、彼は、自分の腕に涙が伝ったことに気づいて、わたしの頬に触れた。何度か指でその涙を拭って、何度か「まい」とわたしの名を呼んで、それ以上は何も言わなかった。
ユウ君の隣にわたしが居るということや、その腕の中にわたしが居るということは、なんだかもうとっくの昔から続いていたことのようで、2人とも何も驚かなかったし、そこは静かだった。
まるで1人で穏やかに眠るときのように、誰もいないみたいに
吐息も、温度も、何もかもが自分の一部のようで
なのに、まるっきり全部を包み込んでしまうような、大きなまん丸の愛の中に2人で手を繋いですっぽり入ったようだった。
いつもの情熱や、あっけらかんとした愛のやり取りや、胸打つようなトキメキや喧嘩したときの激しい憤りはどこにも見当たらなくて、
その初めて一緒に眠る夜がこんなにもふつうで穏やかで、
わたしには、それが、ただ嬉しかった。
残り2985文字
<6月にユウ君に5年越しに会って、初めて一晩一緒に眠った日のこと>
自分が人を愛するときに
それがどんな感覚で
どんなに尊くて
どんなに不動で一途かどうか
それは自分にとってずっと、生まれてこのかた当たり前のことだったから
そうやって自分に愛された誰かが、どんなふうに感じるかは、知る由もなかった。
ときどき誰かに、その愛の深さや大きさのことを指摘されても、ピンと来たことは一度もなかったし、
むしろ、誰かが誰かを愛するのを見ながら、そこにたくさんの矛盾を孕んでいることが
とにかく不思議で、どうして人は、愛するものをただ愛する代わりに
いろいろなことを複雑に、難しくするんだろうといつも
そう思っていた。
わたしは、自分とおなじように人を愛する人を、ほとんど見たことがなかった。
そして、わたしから愛された人間は、そのスケールがどんなものかがわからなくて、大抵怖くなって逃げ出した。
これまで数えきれぬくらいにそれを経験してきたので、辛かったけど仕方ないと思うこともあって、誰もがわたしのような愛し方をするわけではない、ということだけは学んだつもりだった。はたまた自分は欠陥だらけなのか、愛し方を間違えているのだと思うしかなかった。
自分に愛されることは、そんなに突然逃げ出すくらいに嫌なものなんだな。
わたしはそれがとてつもなく悲しかったし、一生懸命愛そうといろんなことを試したけど、自分を歪めることも結局上手にできなくて、最後までずっと、ひとりだった。
○
旅行帰りで疲れたわたしが先にベッドに入ると、ユウ君は床でストレッチをしていた。
ゴロンと動いている姿が可愛くて、愛おしくて、目を瞑って運動している間にこっそりベッドから抜け出して、邪魔しないようにストレッチ中の彼の頭の上にしゃがんで、黙ってキスをした。
「うわぁッ 不意打ち来たァッ」と暴れたユウ君だった。
ユウ君のリアクションはいつも80年代ばりにダサくて安心する。
その後満足したわたしはモゾモゾとベッドに入り、いつもの定位置で小さく丸くなった。ストレッチを終えたユウ君がやベッドの奥側に潜り込んできて、まるで何年も一緒に同じベッドで眠ってきた相手のように、そのまますっかり何事もなかったかのように目を閉じた。
彼は、何度かわたしの髪を撫でて、何度かキスを繰り返し、「おやすみ」すら言わなかった。
そのうちユウ君の吐息が聞こえてきて、なんたる安心だろうとわたしはずっとその背中を眺めていたくなった。
そして、ふいに、その腕のなかにすっぽり収まったときにそれは起こって、
それは今まで経験したことのないような衝撃だったんだ。
その温かくて柔らかな手が、まるで春色の花束をそっと抱くかのように、わたしの細い肩を包み込んで、ゆっくりと髪を撫でられて、ゆっくりと抱きしめられたり、キスをされたりする中で感じたもの。
それは、わたしが、自分が誰かを愛し、そして大切に大切に抱きしめるときの
自分そのものだった。
それは、ショックだった。
最初は何が起こったのかよくわからなくて、ただ5、6年越しにようやく会えたことで、念願叶って彼の腕の中に居ることや、ようやく抱かれて眠ることが嬉しかったのかとおもった。
でもわたしは、自分の身体に、たまらなく大切に触れるその感触をみて、すぐにわかった。
「こんなふうに、誰かを愛していたんだ わたしは。」
初めて目の前で、鏡のように見せつけられた瞬間だった。
それは、これまで誰に愛された時よりも、桁違いに大きく、優しかった。
過去、わたしが愛した人は全員去っていった。男も、女も。
だから、わたしは自分の愛し方には問題があるのだといつしかそう思うようになっていた。
それは、自分が人に嫌われるようなことをして失敗したり、過ちを犯して誰かを失うことに比べたら、はるかに辛いことだった。
愛すれば愛するほど、何かを傷つけたり、何かは壊れるのだから。
ユウ君の腕の中は、底なしに、優しかった。
信じられないような柔らかな温かさで、そこは無条件に守られていて、まぎれもなく永遠で、穏やかで、一寸違わずに間違いのない場所だった。
そして、そのショックは自分が感じるのとまた同じように、彼にとってそれは酷く自然なありかたであって、まさか自分の腕の中にいる女が、こんな想いをしているなどとは思ってもいなかったことだろう。
わたしはそのショックと、愛の雷に打たれたみたいに、気づいたら率直に泣いていた。
彼に久しぶりに会えたことの嬉しさよりも
初めてベッドの中で抱きしめられたときめきよりも
わたしは、こんな風に人を愛していたんだ。
誰にも受け止めてはもらえなかったけれど、それで良かったんだ。
そう思うと涙がほろほろ次から次へと流れてきて、止まらなくなった。
それは本当は人を傷つけたり、人が去っていったり、嫌われるようなものではなく、
こんなにも甘く優しく、まるで逃げ出したくなるほどに神聖で、本物だった。
わたしはそして、ユウ君の腕の中から逃げ出す代わりに涙した。
ここに、わたしが誰かを心底愛するのとまったく同じように
愛し、抱きしめられる人がいる。
当たり前のように、キョトンとしながら、わたしの身体を撫でて、涙を拭っていた。
わたしの目の前にその人はいて、
2人で何度も何度もしっぱいを 重ねては、傷つけ合った5、6年の果てしない時間を経て
「まいを、大事にしたいんだ」
「本気です」
「愛してる」
と、わたしへの愛を諦めないで、いてくれた。
わたしたちは明るい時間の約束通り、セックスをしなかった。
数年ぶりに会って、いきなりセックスはダサいからというユウ君の持論により、わたしたちは抱き合い、寄り添い、ひんやりした足を重ねあわせ、添い寝で朝まで眠った。
私のことをこんなにも愛してくれるなんて。と思うひとは、これまで何人かいたかもしれない。
私のために、命すら差し出していいという人もいた。
でもそういう相手が、自分と同じような愛し方だったかといえば全然違い、わたしが同じように愛せたかといえばそれは本当にまた、別の話だった。
そして、
こんなにも私と同じように人を愛するひとが、今1人この世界にいる。
そしてその人はわたしのことをひたむきに、大切に見ていてくれていて、
わたしもまた、彼のことを同じように見ていることは
この世界で最も祝福すべき幸せなことのうちのひとつだと思う。
ふたごの弟みたいなユウ君。
わたしと同じような激しさと、我の強さと、同時に繊細さを持ち合わせていて、わたしが誰かを愛し、優しく撫でるのと同じようにする人。
いつか昔、ユウ君を守り、救いたかったのに失敗した私は、今度こそ
彼を守り抜くことができるんだろうか。
全然自信も無い中で、
わたしたちは
また、新しい日々にチャレンジしている。
誰かを愛するのではなく、愛する人を愛するという、本当のチャレンジに。

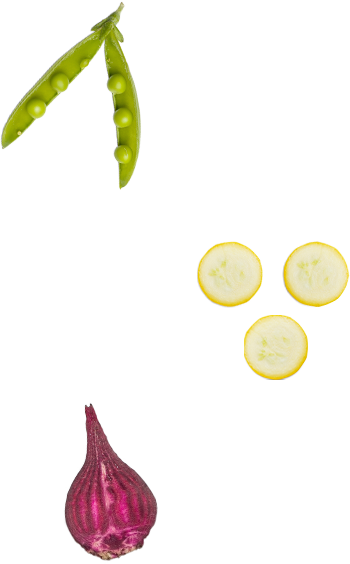



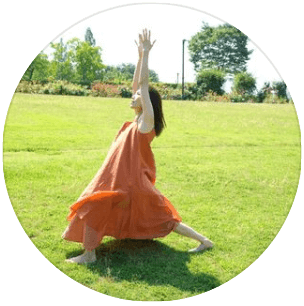 世界中に愛と癒しが行き渡り、みんなが支え合って生きてゆけますように💕
世界中に愛と癒しが行き渡り、みんなが支え合って生きてゆけますように💕



