誰かを愛する優しさのことや、心底愛されるよろこびのことを
思い出そうとしている、5月のおわり。
一難去って、また一難と思いながら、這いずるようにして光に向かう。
手にしたかった愛のことや、過去に見送るものや、手放すものや、今この瞬間から芽生えてゆく軽やかな愛のこと。
一難さって、また一難なのか、捨てる神あり拾う神ありというのか。
いつかむかし、わたしが全身全霊で愛そうとした双子の弟みたいな子がいて、わたしたちはよく喧嘩をした。たくさん傷ついたし、辛い時間を課されたあと、もう二度とお前のことなど信じないと誓ったんだった。
そのあともずっと愛を囁かれても、わたしは二度と耳を貸さずに、まるで復讐でもするかのように彼のガラスのハートを粉々に砕きつづけた。
彼をみているとまるで、自分がそこに誰かを変わらずに一途に愛し続けるのと同じように、なにがあっても、明日世界が終わっても、絶対的にそこに鎮座している「愛してる」を感じた。
だからわたしは復讐中もたまに、泣きながら「愛してるって言って」と突然彼に言った。
その「愛してる」の安定感たるや不思議なほどの瞬発力でこちらに跳ね返り、世界にまだ存在している「愛してる」の魔法を、まるで自由自在に使うみたいにしてわたしはそれを見てただ、安心した。
誰かを愛するとき、最終的というか、究極的には、その相手を個人的に愛する次元を越えるのだと思う。
そういう意味で、わたしは彼の愛を個人的に捉えているわけではなくて、なんというか「こんなふうにちゃんと人を愛する人が、この世界にはわたしの他にもいる」という確認作業みたいなもので、
おそらく彼も、同じような愛をわたしのなかに見出している部分もあるのかもしれない。
それは不思議なつながりで、初めてあった時にあまりに懐かしさを感じたときから今も変わらずにむかつくし、懐かしい。
過去生でも仲が良かったとおじいちゃん先生に言われた。
どれほど重く深い悲しみを、泣いて泣いて泣いて表現しても、彼はそれをスルッと掃除機で吸うみたいにして受け止める。
受け止めるというとちょっと語弊があるし、かといえスルーされているわけでもなく、なんというか、自分の重たさが彼の前では不思議と軽く無重力空間に変化するのだった。
もしかするとそれは、彼もまた同じように何か重たい時間を背負ったことがあることも関係してるかもしれないし、単に愛のなせるわざなのかもしれない。それは、わからない。
一度だけ、この世のものとも思えないほど艶やかな、甘く濡れたキスをしたことがあるだけで、セックスもしたことがなければデートしたこともない弟みたいな人がいて、そこにはいつも愛があって、とりあえず良かった。
不思議な初夏だ。

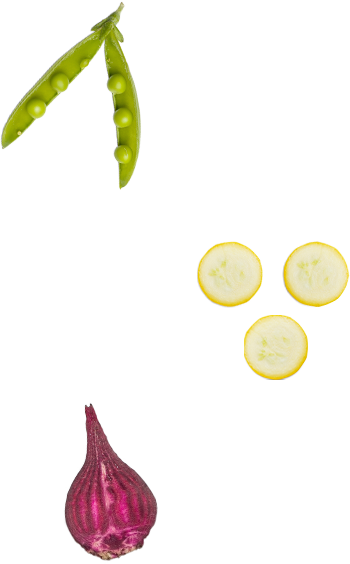



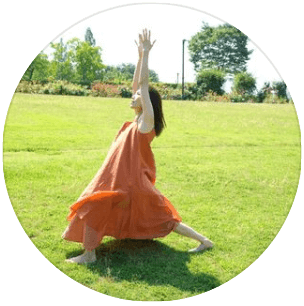 世界中に愛と癒しが行き渡り、みんなが支え合って生きてゆけますように💕
世界中に愛と癒しが行き渡り、みんなが支え合って生きてゆけますように💕



